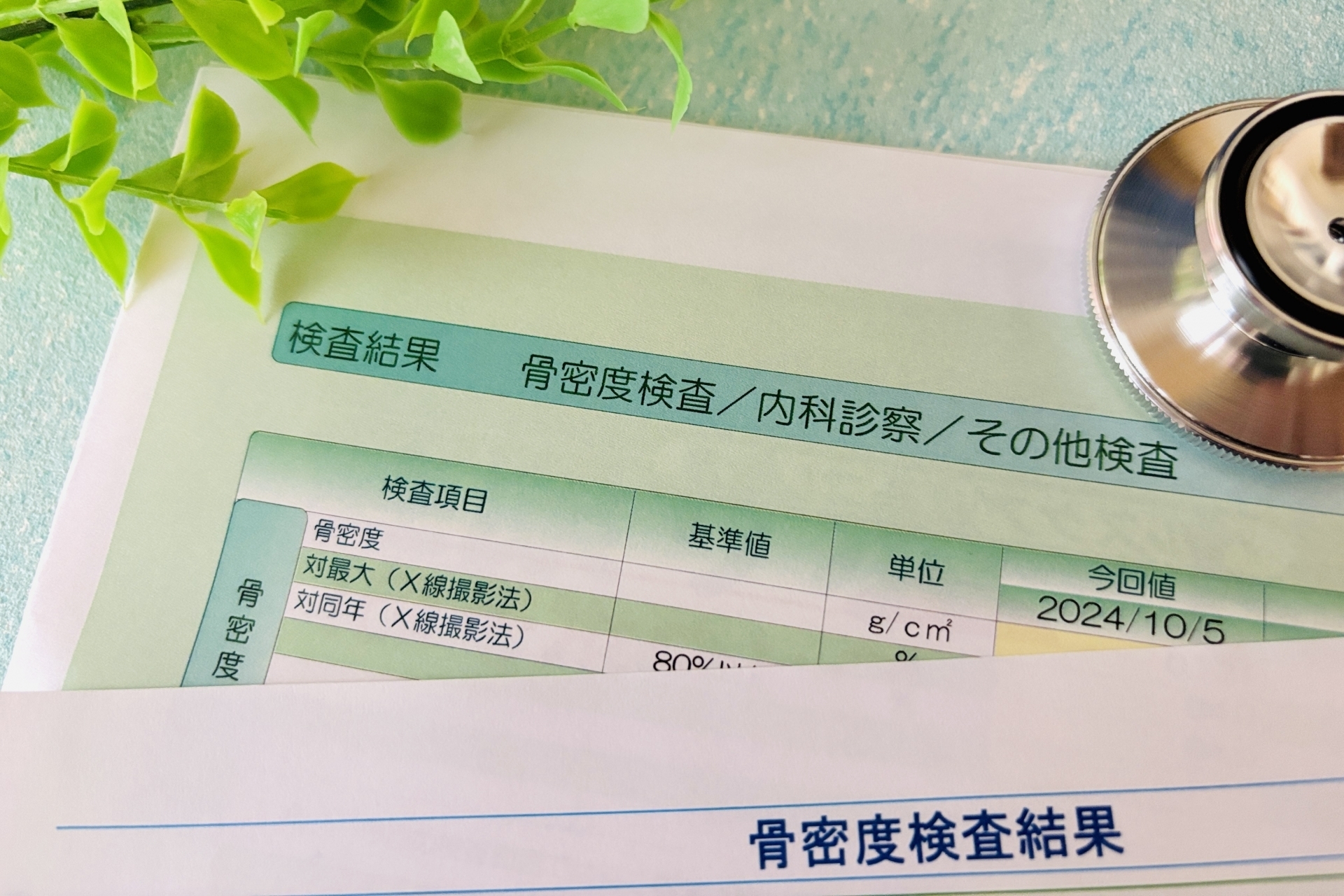
「骨密度が低いですね」と健診で言われたことはありませんか?
骨密度とは、骨の中にどれだけ“カルシウムなどのミネラル成分が詰まっているか”を表す指標です。
つまり、骨の「強さ」を数値で表したもの。
この骨密度が下がると、ちょっとした転倒でも骨折しやすくなったり、姿勢が崩れやすくなったりします。
骨はただの“硬い棒”ではなく、実は常に新陳代謝を繰り返している生きた組織です。
古い骨を壊す「破骨細胞」と、新しい骨をつくる「骨芽細胞」がバランスよく働くことで、骨は丈夫に保たれています。
ところが、このバランスが崩れると、骨密度は少しずつ減っていきます。
なぜ骨密度は減少してしまうのか?
骨密度が低下する大きな理由は「加齢」と「生活習慣」です。
加齢によって、骨をつくる働きが弱くなり、同時に女性では閉経後のホルモン変化(エストロゲンの減少)によって骨がスカスカになりやすくなります。
男性でも筋力や運動量の低下、偏った食事、喫煙・飲酒などが重なることで、同じように骨密度は落ちていきます。
さらに、現代人は「立つ・歩く・しゃがむ」といった骨に刺激を与える動きが極端に減っているのも問題です。
骨は“負荷がかかるほど強くなる”性質をもっており、運動不足は骨の弱体化を進める大きな要因になります。
骨密度が低下するとどうなる?
骨密度が低下すると、最も心配されるのが「骨粗しょう症」です。
骨がもろくなり、軽い衝撃でも骨折してしまう状態です。
特に多いのが「大腿骨の付け根」「背骨(圧迫骨折)」「手首」の骨折。
これらの骨折は寝たきりや介護のきっかけになることが多く、“健康寿命”を大きく左右します。
また、骨折までいかなくても、骨が弱くなると姿勢が悪くなり、背中が丸くなる、身長が縮む、呼吸が浅くなるなど、体全体に影響します。
骨の問題は見た目や動きのしなやかさにも関係してくるのです。
骨密度を増やすためのポイント
では、骨密度を維持・向上させるにはどうすればいいのでしょうか?
実は、難しいことをする必要はありません。
日常の中で少し意識を変えるだけで、骨はしっかり応えてくれます。
① 「歩く」「立つ」を増やす
骨は“重力の刺激”で強くなります。
エレベーターを階段に変える、買い物を歩いて行くなど、日常の中で骨に刺激を与える時間を増やしましょう。
特に「かかとに体重が乗る」動きは骨への刺激が大きいといわれています。
② 筋肉を動かす
筋肉は骨を引っ張ることで骨に負荷をかけます。
太ももやお尻など大きな筋肉を動かす運動(スクワット、つま先立ち、片脚立ちなど)はとても効果的です。
無理のない範囲で「ふらつかずに行える強度」で継続することがポイントです。
③ 栄養をしっかり摂る
骨を作る材料である「カルシウム」だけでなく、その吸収を助ける「ビタミンD」や「ビタミンK」も重要です。
小魚、乳製品、納豆、きのこ類などを意識して取り入れましょう。
また、朝の日光浴でビタミンDが体内で合成されますので、5〜10分の散歩でも効果があります。
④ 良質な睡眠とストレスケア
骨をつくるホルモン(成長ホルモン)は睡眠中に多く分泌されます。
夜更かしを避け、しっかり休息をとることも骨の健康には欠かせません。
また、慢性的なストレスはホルモンバランスを崩し、骨の代謝を低下させる原因にもなります。
「骨は生きている」から、今からでも間に合う
骨密度は年齢とともに低下するものの、「完全に戻らない」わけではありません。
骨は筋肉と同じように刺激に反応し、つくり変わる力を持っています。
つまり、今日からの生活の工夫で“骨は強くなれる”のです。
「転ばないように気をつける」だけでなく、「転んでも折れない体をつくる」こと。
それが、本当の意味での骨密度対策です。
健康寿命を延ばすために、まずは小さな一歩から始めてみましょう。




